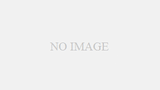低金利時代が終わり、いよいよ金利のある世界が戻ってきました。でも、「じゃあ、どこに資産を預ければ安心で、しかも賢く増やせるの?」と悩んでいませんか?この記事では、銀行預金に留まらない資産の預け先や、金利上昇局面で注目すべき運用方法を徹底解説!資産を守りながら着実に増やしたい人のための、最新お金戦略を紹介します!
金利のある世界が再びやってきた!なぜ今、資産の預け先を見直すべきなのか?
ここ数十年、日本は「超低金利時代」と呼ばれる特殊な状況が続いてきました。預金金利はほぼゼロ。資産を銀行に預けていても、ほとんど増えることはありませんでした。ですが、2024年以降、世界の金融環境は大きく変化しています。日銀は2024年にマイナス金利政策を解除し、実に17年ぶりに金利を引き上げました。そして2025年に入り、その影響が本格的に家計や企業に及び始めています。
この変化は、「お金の置き場所=資産の預け先」を見直すタイミングが来たことを意味しています。ただ銀行に預けるだけでは、お金の価値は守れない。むしろインフレや税金に負けて、実質的な資産価値は目減りしていく可能性すらあります。
金利があるということは、「お金に価格がついた」ということ。つまり、お金を持つコストと、預けておくことで得られるリターンが復活した、ということなんです!そのインパクトと重要性、そして今見直すべき理由を、ここから詳しく解説していきます!
金利上昇は「ただの経済ニュース」じゃない!あなたの財布にも確実に影響する
まず理解しておきたいのが、「金利が上がった」と聞くと、多くの人が「住宅ローンが上がる」とか「借金の利息が高くなる」といった“ネガティブ”な面ばかりをイメージしがちですが、それは半分だけ正解です。
実は、金利上昇には“ポジティブな側面”もあるんです!
たとえば、以下のような影響があります。
• 預金金利の上昇:大手銀行でも、普通預金金利が0.001% → 0.02%など、20倍以上になるケースも。定期預金ではさらに高くなる可能性もあります。
• 債券利回りの上昇:国債や社債などの利回りが上がり、より堅実に資産運用が可能に。
• 配当利回りの魅力再認識:企業も資金の使い道を見直すため、株主への還元が増えたりするケースも。
つまり、「お金を持っているだけ」の人にとっても、行動次第で恩恵を受けられる状況が生まれてきたというわけです。
インフレと金利の関係を知らないと、資産はジワジワ減っていく!
ここでもうひとつ重要なのが、「インフレ」と「金利」の関係です。
日本は長らくデフレ状態にありましたが、2022年以降は物価がジワジワと上がり続けています。食料品、電気代、ガソリン代、日用品…。実感している方も多いと思います。「えっ、こんなに高かったっけ?」と感じたこと、ありますよね?
これはつまり、「同じ1万円でも買えるモノが減っている」状態。お金の価値が下がっている=実質的な資産が減っているということなんです。
金利がある世界では、このインフレに対抗できる「防波堤」として、金利付きの金融商品が有効になります。たとえば年利3%の債券を持っていれば、インフレ率が2%でも、実質的に1%分資産を増やせる可能性があるんです。
銀行にただ眠らせているだけのお金には、そういった「防衛力」がありません。だからこそ、今このタイミングで「預け先」を見直す必要があるんです!
資産の預け先=「安全な場所」とは限らない
日本人の多くは「とりあえず銀行が安全」と考えがちですが、それは本当に正しい選択なのでしょうか?
確かに銀行は元本保証があり、預金保険制度(1,000万円+利息まで保証)もあります。でも、今のようなインフレ下で、金利がわずかしかつかない状況では、「安全だけど減り続ける場所」になってしまうんです。
たとえば、物価が年に2%上昇し、預金金利が0.001%しかなければ、毎年1.999%の実質損をしている計算になります。つまり、「預金しているつもりで、気づかぬうちに資産を減らしている」んです。
資産を守るという意味では、インフレ対策として少しでも増やす努力をすることが、実は“本当の安全”に繋がる時代になっているんです。
なぜ今、資産の預け先を「自分で考えること」が求められているのか?
2025年現在、日本でも海外でも金融政策は激しく変化しています。特に、アメリカや欧州では金利が高止まりする一方で、経済の減速懸念も出てきています。こういった時代では、金融機関や政府が常にベストな選択をしてくれるとは限りません。
「誰かに任せれば安心」という時代は、もう終わったんです。
SNSやネット情報の拡散で、あらゆる投資情報が手に入る今だからこそ、自分の資産を「どこに預けるか」を自分で調べ、考え、判断する力が求められています。
とはいえ、「投資」と聞くだけで不安になる人も多いですよね。だからこそ、この記事では次の小見出しで「安全性」と「金利の恩恵」のバランスが取れた資産の預け先をわかりやすく解説していきます!
このように、金利のある世界が戻ってきた今、「資産を預ける場所」に無頓着ではいられません。預金口座に眠っているだけのお金を、どう動かすか。その選択が、5年後・10年後の未来に大きな差を生む時代です。
銀行預金だけじゃもったいない!金利上昇で注目される安全な資産運用先とは?
これまで「とりあえず銀行に預けておけば安心」と考えてきた人も、金利上昇の波に乗って「もっと効率よくお金を働かせたい!」と思い始めているかもしれません。でも、投資ってなんだか怖い…。損したくない…。その気持ち、よくわかります!
そんなあなたに伝えたいのが、「資産運用=ハイリスク・ハイリターン」ではないということ。金利のある今の時代、安全性と収益性のバランスがとれた“堅実な資産運用先”がたくさん登場してきているんです!
ここでは、2025年現在注目されている「銀行以外の安全な資産運用先」をピックアップし、その特徴とメリットをやさしく、かつ実用的に紹介していきます!
まず知っておきたい!「安全な資産運用先」の基準とは?
「安全な資産運用」と聞いて、どんな条件を思い浮かべますか?元本保証?リスクが少ない?情報が透明?人によって定義は異なるかもしれませんが、共通して大切なのは次の3つです。
1. 元本が大きく毀損しにくいこと
2. 流動性がある(必要な時に引き出せる)こと
3. 信用力が高い発行体や運営元であること
つまり、ギャンブルのような投資ではなく、資産を安定的に守りながら、じわじわと増やす運用先こそが「今、注目されるべき場所」なんです。
① 個人向け国債(変動10年)は今こそ本領発揮!
まず真っ先におすすめしたいのが「個人向け国債(変動金利型・10年満期)」です。
これ、地味なんですけどめちゃくちゃ優秀なんです!
• 元本保証:政府が発行しているため、破綻リスクはほぼゼロ
• 金利上昇に連動:名前のとおり「変動金利」なので、将来的に金利が上がれば、それに応じて利率もアップ!
• 最低金利保証あり:金利が低くても年0.05%が最低保証されているため、損することはない構造
• 1万円から購入可能:少額から始められる安心感
2024年〜2025年にかけては、金利がじわじわと上昇しており、まさに「変動型」の魅力が生きてくるフェーズです。しかも、中途換金も可能なので、いざという時に資金を引き出せるのも安心ですね。
② 定期預金も“ネット銀行”に注目すると世界が変わる!
「やっぱり銀行が安心…」という方には、ネット銀行の定期預金をおすすめします!
大手メガバンクの定期預金金利は、いまだに年0.002%程度が主流ですが、実はネット銀行では「年0.2%~0.3%」という金利を提示しているところも珍しくないんです!
例えば2025年3月時点では以下のような例があります:
• あおぞら銀行BANK支店:普通預金で年0.2%
• SBI新生銀行:パワーダイレクト円定期預金で年0.25%
• 楽天銀行や住信SBIネット銀行も定期で0.2%超のプランを提供
同じ「銀行預金」でも、選び方ひとつで100倍以上の差が出る時代です!特にネット銀行は、預金保険制度の対象でもあり、万が一の破綻でも1,000万円+利息までは保証されます。安心しながら、より良いリターンが得られる選択肢なんです!
③ 高格付けの社債(個人向け)もリスク抑えて運用できる
「少しだけ利回りを上げたいけど、リスクは極力抑えたい」という人にピッタリなのが「高格付けの社債」です。
たとえば:
• トヨタファイナンス
• ソニーグループ
• NTTファイナンス
などの大手企業が発行する社債は、信用リスクが低く、金利も年1.0%〜1.5%程度と悪くありません。
もちろん、元本保証はありませんが、発行企業の信用力が高ければ、そのリスクはかなり限定的。5年程度の期間で満期償還されるものが多く、満期まで保有すれば利回りが確定するという“シンプルさ”も魅力です。
④ 金利上昇局面で見直される「外貨預金」
ここで少し中級者向けになりますが、外貨預金も金利上昇時には注目される資産運用先のひとつです。
たとえば、米ドル建ての定期預金では、年4~5%の金利がつくケースもあります(2025年3月現在)。円で預けるより、はるかに高いリターンが期待できますよね。
ただし、為替リスク(ドル円の変動)があります。円高になると、元本割れする可能性もあるので、以下のような工夫が必要です:
• 為替分散として少額から始める
• 定期的に積み立てて、平均取得単価を平準化する
• 為替ヘッジ付きの商品を選ぶ
うまく活用すれば、円安の恩恵と金利収入の両方が狙える選択肢です!
⑤ 「投資信託(債券型)」も安定運用にピッタリ!
「投資」と聞くと株のイメージが強いかもしれませんが、債券型の投資信託ならリスクを抑えながら運用可能です。
• 国債中心のファンド
• 社債を中心に分散されたファンド
• 短期債券ファンド(利回り安定)
など、商品ラインナップも豊富。自分のリスク許容度に合わせて選べます。
さらに、少額から積み立てられる「つみたてNISA」や「iDeCo」といった非課税制度を使えば、税制面でも大きなメリットがあります!まさに、堅実派にとってはぴったりの資産運用法なんです。
「安全だけど増やせる」場所は、探せばちゃんとある!
銀行預金が“安全だけど増えない”場所だとすれば、今の時代には“安全かつ増やせる”資産の預け先がしっかりと存在しています。
• 個人向け国債
• ネット銀行の定期預金
• 高格付けの社債
• 外貨預金(注意付き)
• 債券型投資信託
こういった運用先を組み合わせることで、「リスクを抑えながらお金を働かせる」ことが現実にできるんです!
賢い人が実践している!金利のある世界での「分散投資」の具体的なやり方
「分散投資って聞いたことはあるけど、具体的にどうすればいいの?」という人、多いと思います。やみくもにいろんな商品に手を出すのは、分散どころかリスクの拡大にもなりかねません!
特に金利のある世界に突入した今、分散投資のやり方も時代に合わせて進化してきています。大切なのは、「どの商品に」「どのくらいの割合で」「どんな目的で」資産を分けていくかということ。
この章では、初心者でも実践できる分散投資の考え方から、金利上昇局面で有効な具体的なポートフォリオ例まで、じっくり解説していきます!
そもそも、なぜ「分散投資」が重要なのか?
投資において“分散”は、最強のリスクヘッジ方法です!
たとえば、1つの商品に全資産を預けていた場合、それが値下がりしたら一気に損失が出ます。でも、いくつかの商品に資産を振り分けていれば、一部が下がっても他でカバーできる。これが分散投資の基本的な考え方です。
さらに金利のある世界では、以下のような追加メリットもあります。
• 金利上昇による債券商品の収益アップ
• 株式市場の変動時にも一定の収益源を確保できる
• 為替や物価変動によるリスクを抑えられる
つまり、複数の収益源を確保することで、どんな相場でも資産を守りやすくなるというわけです!
金利上昇局面で意識すべき分散の「3軸」
分散投資を成功させるには、ただ商品をバラバラに買えばいいわけではありません。重要なのは、「分散の軸」を意識すること。特に2025年の金利上昇局面では、次の3軸で分けて考えることがカギになります。
1. 資産クラスの分散(債券、株式、現金、不動産など)
2. 地域の分散(国内、海外、新興国など)
3. 時間の分散(積立、定期購入、買うタイミングを分ける)
この3つの視点をバランスよく取り入れることで、一時的な市場の波に流されない、安定した資産形成ができるようになるんです!
金利がある今こそ活かせる!具体的なポートフォリオ例(初心者向け)
では実際に、どんな分散がオススメなのか?ここでは「投資初心者」を想定して、金利上昇を踏まえた具体的なポートフォリオ例をご紹介します。
【例:500万円の資産を運用する場合】
• 現金・普通預金:100万円(20%)
• 生活防衛資金として確保
• 個人向け国債(変動10年):150万円(30%)
• 安全性+金利連動の収益を狙う
• 国内株式・高配当ETF:100万円(20%)
• 株主還元の高い企業を厳選して安定収入を狙う
• 先進国債券ファンド(為替ヘッジあり):75万円(15%)
• 外貨資産でインフレ対策しつつリスクは抑える
• 外国株式インデックス(つみたてNISA枠で):75万円(15%)
• 長期目線でリターン重視の積立投資
このように、資産を複数のカテゴリに分散することで、リスクを抑えつつ、金利上昇の恩恵をうまく取り込める構成になります!
「自分に合った分散」のために必要な3つのステップ
実は、理想的な分散投資の形は人それぞれ違います。年齢、収入、家族構成、目標金額…。こうした条件によって「リスクの取り方」も変わってくるからです。
自分に合った分散のためには、以下の3ステップを踏むのが大切です!
1. 目的を明確にする(老後資金?子どもの教育費?住宅購入?)
2. リスク許容度を見極める(値動きに耐えられるか?)
3. ライフスタイルに合った商品を選ぶ
たとえば、「10年後に住宅購入資金を確保したい」という人であれば、比較的リスクを抑えた債券中心の運用が合っているかもしれませんし、「30代で老後資金を積み立てたい」という人であれば、多少リスクをとって株式やインデックスファンドに重きを置くのが正解かもしれません。
金利上昇=債券が不利になるってホント?誤解に注意!
「えっ?金利が上がると債券って値下がりするんじゃないの?」という声もあります。たしかに、既存の債券価格は金利上昇で下がります。でも、それは**「すでに保有している債券を売却する場合」の話なんです。
債券を「満期まで保有」すれば、元本+利息は確実に受け取れます。さらに、今後発行される新しい債券は、金利が上がったぶん高利回りになります。
つまり、「これから債券に投資する人」にとっては、むしろチャンス!なんです。
投資信託でも、金利上昇局面に対応した「短期債型」や「インフレ対応債型」など、商品のバリエーションが広がっています。しっかりと選べば、安定運用とリターンの両立が可能です!
実践に移すには?まずは「つみたて」と「NISA・iDeCo」から
分散投資を始めたいけど、いきなり大金を動かすのは怖い…。そんな方にオススメなのが「つみたてNISA」や「iDeCo」です!
• つみたてNISA:年間40万円までの投資で得た利益が非課税(20年間)
• iDeCo:掛金が所得控除、運用益も非課税、受取時にも控除あり
しかも、毎月数千円から積み立てが可能。長期で少しずつ積み上げていくことで、「時間の分散」も実現できます!
リスクを最小限にしながら投資を始めたいなら、まずはこの2つの制度を最大限活用するのが賢いやり方です。
分散投資は、「リスクを避けるための逃げ道」ではありません。むしろ、資産を安定的に増やすための“戦略”です!金利のある世界では、選択肢が増える分、判断の精度が問われます。
インフレ時代に強いのはこれ!金利と相性の良い資産の特徴と選び方
物価がどんどん上がっていくインフレ時代。スーパーに行って「え?また値上がりしてる…」と感じたこと、きっとありますよね。2024年以降、日本でも食品や日用品の値上げが当たり前になり、「同じ金額で買えるものが減っている」実感を持っている人が急増中です。
そんな時代には、「現金のまま持っている=どんどん目減りする」というのが大問題。だからこそ、インフレに強い資産を持つことが、自分のお金の価値を守るカギになります!
今回は、「金利がある時代」において、インフレに強く、かつ運用もしやすい資産の特徴と選び方をわかりやすく解説していきます。
インフレに強い資産=「モノ」に近いもの
まず押さえておきたい基本は、インフレが起きると、「お金の価値が下がり、モノの価値が上がる」ということ。つまり、モノやモノに連動した資産を持つ人が得をしやすいのがインフレ時代の特徴なんです。
じゃあ「モノ」って何?というと、たとえば次のような資産です。
• 不動産(土地・建物)
• 商品(コモディティ):金(ゴールド)・原油・農産物など
• インフレ連動債
• インフレに強いビジネスモデルを持つ企業の株式
• REIT(不動産投資信託)
これらは、インフレによって価格や収益が増える構造を持っているので、実質的に“価値が下がりにくい”という強みがあるんです。
金(ゴールド)はインフレの“伝統的な守り神”!
インフレ対策としてもっとも有名なのが**金(ゴールド)**です。金は国境や通貨を超えて価値を保ち続けてきた資産で、どんな時代でも“最後の資産防衛手段”として人気があります。
2024〜2025年にかけては、アメリカや欧州の金融不安、世界的な地政学リスクも相まって、金価格は歴史的高値を更新中。インフレへの警戒感が高まると、金に資金が集まりやすくなる傾向があります。
金の特徴:
• 利息はつかないが、インフレ時には価格上昇が期待できる
• 世界共通の価値を持つ
• 政府の金融政策に左右されにくい
ただし、価格の上下はあるので、短期的に利益を狙うより「インフレ保険」として一部保有しておく、というスタンスがベストです。
不動産は“インフレに強い資産”の代表格
不動産は、インフレ局面で最も恩恵を受けやすい資産のひとつ。なぜなら、物価が上がる=建設費用や土地価格も上昇するため、不動産自体の価値が高まりやすいからです。
さらに、家賃収入も物価に連動して上昇するケースがあるため、「収益がインフレに合わせて増える」というメリットも!
特に都市部の住宅や物流倉庫、賃貸アパートなどは、2025年現在も高い需要があります。最近では「不動産クラウドファンディング」など、少額で不動産投資に参加できるサービスも増えていて、初心者でも一歩を踏み出しやすい環境になっています。
ただし、物件選びや地域選定によってリスクが変わるため、「利回り」や「空室リスク」などをしっかりチェックするのが大切!
REITは「不動産×分散投資」の賢い選択肢!
不動産に興味があるけど、管理とか手続きが面倒…という人には、「REIT(リート)」という選択肢もあります。REITは、不動産に投資する投資信託のようなもので、複数の物件に分散投資されているのが特徴です。
2025年現在、日本のREIT(J-REIT)は金利上昇の影響で一時下落したものの、インフレ対策や配当狙いの投資先として再評価されています。利回り3〜5%程度の銘柄も多く、安定的な収入を得られる点が魅力!
さらに、少額(1口数万円程度)から購入できて、証券会社の口座があればすぐに始められる手軽さもポイントです。
インフレに強い株式は「価格決定力」がある企業!
「株ってインフレに弱いんじゃ…?」と思う方もいるかもしれませんが、それは一部だけ。実は“インフレに強い企業”の株式は、インフレ局面でむしろ利益を伸ばしやすいんです!
たとえば:
• 日用品メーカー(値上げしやすい)
• 電力・ガスなどの公共インフラ(料金調整が可能)
• 食品関連企業(価格転嫁が進んでいる)
• エネルギー・資源関連(価格上昇に連動)
これらの企業は、「自社で価格を決められる=価格決定力がある」ため、インフレによるコスト上昇をうまく転嫁できるという特徴があります。
投資信託やETFを通じて、こうした企業に分散投資するのもオススメです!
インフレ連動債って知ってる?国が発行する「インフレ保険」
もっと堅実派な人にオススメなのが、「インフレ連動債(物価連動国債)」です。これは、国が発行する債券の一種で、物価(CPI)に連動して元本や利子が変動する仕組みになっています。
つまり、物価が上がれば利息も元本も増える、という“インフレ耐性”があるんです!
日本ではまだあまり一般的ではありませんが、証券会社を通じて購入することが可能で、特にインフレが続く局面では非常に心強い選択肢になります。
インフレ対策のコツは「複数の武器」を持つこと
インフレに強い資産は、どれかひとつを選ぶよりも、いくつかを組み合わせるのが正解です。
たとえば:
• 金:5〜10%
• REIT:10〜20%
• 株式(価格決定力のある銘柄):30%
• インフレ連動債や個人向け国債:30%
• 現金・普通預金:10〜20%
こんな感じで、リスクとリターンのバランスをとりながら構成していくと、安定感がぐっと増します!
インフレの時代こそ、資産を“動かす”勇気を!
インフレが続くと、何もしないことがリスクになる時代です。「減らしたくないから預金に寝かせておく」という選択が、実は一番危険だったりします。
だからこそ、少額でも、できることから一歩ずつ。金利のある今の時代には、それに合った資産を選び、組み合わせ、持ち続けることが自分の資産を守り抜く一番の方法なんです!
やってはいけない資産の預け方!金利がある時代に損しやすいNG行動とは?
「とりあえず現金は銀行に置いてあるから大丈夫」
「投資って結局ギャンブルでしょ?だから何もしない」
「よくわからないから保険に全部預けておけば安心」
もし、あなたがこんなふうに考えているなら、要注意です!
金利がある今の時代、知らずにやってしまう“間違った資産の預け方”が、将来的に大きな損失を生む可能性があるんです。
しかも、その多くは「一見、安全そうに見える」ものばかり。ここでは、特にやりがちなNG行動とその理由を具体的に紹介していきます!
① 「ただの普通預金」で資産を眠らせるのは、今いちばんもったいない!
昔からの習慣で「給料が入ったら銀行に入れる」「まとまったお金も預金にそのまま」としている人、多いですよね。でも、これは金利がない時代の話!
2025年現在、メガバンクの普通預金金利は0.001%〜0.002%のまま。仮に100万円を預けても、年間の利息はたったの10〜20円…。これでは、もはやお金が働いているとは言えません。
一方で、物価は年2%〜3%のペースで上がっているため、実質的に「お金の価値が毎年減っている」状態になってしまうんです。
【NGポイント】
• 金利はゼロに近く、インフレに全く対抗できない
• 増えないどころか「目減り」する
• 銀行に預けているだけで、機会損失が大きすぎる
対策: ネット銀行や個人向け国債、流動性のある債券型ファンドなど「安全性+最低限の金利」が期待できる運用先に切り替えるのが大切です!
② 高額な「貯蓄型保険」に資産を寝かせるリスク
「資産運用は怖いけど、保険なら安心そう」と考えて、貯蓄型保険に加入している人も少なくありません。確かに、一定期間後に満期金を受け取れたり、死亡保障がついていたりするメリットもありますが、金利のある今、貯蓄型保険は効率がかなり悪いんです。
【NGポイント】
• 運用利回りが低すぎる(年0.5%〜1.5%程度)
• 解約返戻金が少なく、途中解約すると損する可能性大
• 仕組みが複雑で、手数料やコストが見えにくい
保険商品としての機能はもちろんありますが、「資産運用」の観点では、他の金融商品に比べて圧倒的に非効率。特に、金利が上昇している今は、より高利回り・柔軟な商品がたくさんあるため、“見直しの優先順位が高い資産”と言えます。
③ 「定期預金ならOK」と思ってメガバンクに預けるのも実は損!
定期預金なら普通預金よりはマシ…と思いきや、2025年現在、大手銀行の定期預金金利もせいぜい年0.002%〜0.01%程度。これでは、1年間預けて数十円しか増えません。
ところが、ネット銀行では同じ定期預金でも年0.3%〜0.5%台の金利を提示しているところもあり、100倍以上の差が出ているケースもあるんです!
【NGポイント】
• 金利が低すぎて、インフレに完全に負ける
• ネット銀行を活用しないのは、情報格差による損失
• 「安心だから」と思って預けるほど、長期的に差が開く
対策: 同じ「定期預金」でも金融機関によって条件は大きく異なるので、常に比較・見直しが必要です!
④ 値動きが怖いからと、投資を完全に避けるのは逆効果!
「リスクを取りたくないから投資はしない」という考え方も、実は金利がある今の時代には“最大のリスク”になりかねません。
なぜなら、インフレによって現金の価値が確実に下がっているから。つまり、資産を守りたいなら、多少なりとも「リスクを取ってリターンを得る」行動が必要不可欠なんです。
【NGポイント】
• 「やらないこと」が一番損になる時代
• 投資=ギャンブルと勘違いして、選択肢を狭めてしまう
• インフレに対応できず、資産の実質価値が減少する
対策: すべてを投資に回す必要はありません。少額から「つみたてNISA」「iDeCo」「国債」などリスクの低いものから始めて、投資への理解と経験を積んでいくことが重要!
⑤ SNSや口コミだけで「なんとなく良さそう」な商品に手を出す
最近ではSNSやYouTubeなどで「この商品が最強!」と紹介される金融商品が増えています。確かに、情報収集の場としては便利なのですが、そのまま鵜呑みにするのは危険!
【NGポイント】
• 商品の仕組みやリスクを理解しないまま購入
• 詐欺まがいの商品も混在(特に“絶対に儲かる”系)
• 資産全体のバランスを崩しやすい
「誰かが儲かった」という話が、自分にも当てはまるとは限りません。大切なのは、自分のリスク許容度やライフプランに合った資産配分を考えることです。
⑥ 長期的な視点を持たず「目先の金利」だけで動いてしまう
2025年現在、金利が上がったことで「今ならこの商品が金利高いから一括で入れてしまおう」と飛びつく人も増えています。
でも、注意したいのは**「金利が高い=ずっと高い」わけではない**ということ。金融政策は変わるし、景気や為替によって利回りも変動します。
【NGポイント】
• 短期的な数字に釣られて資金を固定してしまう
• 長期で見れば損になる可能性がある
• 満期まで資金が動かせず、ライフイベントに対応できない
対策: 金利が高い時でも、全資産を一括で動かすのではなく、「分割」「分散」「段階的」に運用するのが賢いやり方です!
金利がある今こそ、「何もしない」が最大のリスクに!
金利ゼロの時代であれば、「とりあえず預金しておく」という行動も、ある意味では損が少なかったかもしれません。でも、金利のある今は、選択肢が広がっている=選ばなければ損をする時代なんです。
• 普通預金に眠らせない
• メガバンクだけに頼らない
• 保険商品を鵜呑みにしない
• 投資を怖がりすぎない
こうした考え方を1つずつ改めるだけで、資産運用はグッと前向きに進みます!
【まとめ】金利がある今こそ、資産を守り増やすベストな預け先を見極めよう!
2024年に日銀がマイナス金利政策を解除してから、ついに日本にも「金利がある世界」が戻ってきました。今まではお金をどこに置いてもほとんど増えなかったけど、今は違います。お金に“置き場所”を与えることで、確実に働かせることができる時代がやってきたんです!
でも、重要なのは「ただ金利が高い商品に飛びつくこと」ではありません。むしろこれからは、“自分に合った資産の預け先”をきちんと選べる人が勝つ時代なんです。
このまとめでは、これまでご紹介してきた内容をふまえて、「今の時代にふさわしい資産の預け方」を、実践的な視点で整理していきます!
資産の預け先選びで絶対に外せない4つの視点
まず、どんな人でも共通して意識すべき視点がこの4つ!
1. 安全性:元本をしっかり守れるか?信用できるか?
2. 収益性:インフレや税金を加味しても、実質的に増やせるか?
3. 流動性:必要なときに資金を引き出せるか?
4. 分散性:複数の商品・通貨・地域にバランスよく振り分けられているか?
この4つの軸を外さなければ、極端に大きなリスクを背負うことなく、堅実に資産を成長させていくことができます!
今の時代にマッチする“使える”資産の預け先一覧
それでは、金利がある今の時代に実際に活用すべき「具体的な預け先」を整理しておきましょう。
安全性・低リスク重視派におすすめ:
• 個人向け国債(変動10年):元本保証+金利連動
• ネット銀行の定期預金:年0.3%以上の利回りが期待できる
• 高格付けの社債:NTT・トヨタなどの個人向け社債
インフレ対策・実質的なリターン重視派におすすめ:
• 金(ゴールド)・商品ETF:価値の目減りを防ぐ
• REIT(不動産投資信託):安定配当+資産価値上昇の可能性
• インフレ連動債:物価上昇に連動して元本・利息が増える
• 価格転嫁力のある企業の株式・ETF:高収益が期待できる
長期視点で育てたい積立派におすすめ:
• つみたてNISA:非課税で積立、インデックス投資に最適
• iDeCo:老後資金を作りながら節税もできる
• バランス型・債券型ファンド:初心者にも安心な商品構成
失敗しない資産運用のために「やらないこと」もセットで覚えよう!
成功する人が「やっていること」ばかりに目が行きがちですが、実は「やらないことを決めている」人ほど失敗が少ないんです。
以下のようなNG行動を避けるだけでも、資産運用の成果は大きく変わります!
• 普通預金に資産を放置しない
• 保険商品だけに全資産を預けない
• SNSや口コミだけで金融商品を選ばない
• 金利が高いからといって一括で動かさない
• 「投資は怖い」と完全に避ける思考を持たない
一番やってはいけないのは、「何もしないこと」。
動かないことが“安心”ではなく“損失”につながることを、今の時代はしっかり意識しておく必要があります!
自分に合ったポートフォリオを考えるステップ
「じゃあ、結局どうやって組み合わせればいいの?」という人は、以下の3ステップで考えてみましょう。
1. 目的の明確化:いつ、何に、いくら使いたいのか?
2. リスク許容度の確認:どのくらいの変動なら耐えられる?
3. 運用スタイルの選定:積立か?一括か?短期か?長期か?
たとえば、30代独身で老後資金を作りたいなら、「つみたてNISA+REIT+個人向け国債」で攻守バランスよく運用。
一方、60代で退職金の運用を考えているなら、「個人向け国債+ネット定期+一部高配当株」など、守りを意識した構成が合うでしょう。
今こそ“お金の居場所”を見直すチャンス!
金利のある世界が戻ってきたということは、言い換えれば「お金に価値がある時代」に戻ってきたということでもあります。
これまでの「増えない・動かない・学ばない」状態から、「少しずつでも増える・柔軟に動かせる・正しく学べる」環境が整った今、預け方を見直すだけで、5年後・10年後に手元に残るお金が大きく変わるんです。
資産運用というと難しそうに聞こえるかもしれませんが、基本を押さえて、小さく始めて、地道に育てていく。それだけでも、人生の安心感は格段にアップします!
最後に伝えたいこと
あなたのお金は、ただ銀行に眠らせておくためのものじゃありません。
守ることも大事だけど、今の時代は「動かすこと」が本当の意味での守りになることだってあるんです。
ぜひ今日から、自分の資産の“居場所”を見直してみてください。
小さな一歩が、未来の大きな安心につながります!
でも「何から始めればいいかわからない…」そんなあなたへ。
少額からはじめられて、税制優遇もある「つみたてNISA」は、今の時代にぴったりの資産形成ツールです!
初心者でもわかりやすく、時間を味方にして着実にお金を増やすことができます。
まずは証券口座を開設して、月1,000円からでもOK!
“未来の安心”をつくる一歩を、今日から始めてみませんか?